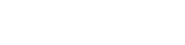遺言書情報証明書の交付請求手続きについて
遺言書情報証明書ってなに?今回初めて交付請求書作成のお手伝いをさせて頂いたので、備忘録も兼ねて大きな流れをお話しさせて頂きます。
その前に…そもそも「自筆証書遺言書保管制度」って?
「遺言書情報証明書」についてお話しする前に、その前提となる「自筆証書遺言書保管制度」について少しご説明させてください。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、自分で手書きで作成する「自筆証書遺言」もそのひとつです。要件を満たせば有効なものとして認められます。
しかし、このタイプの遺言書には、いくつか気をつけたい点がありました。
遺言書が見つからないかもしれない。。。
悪意のある人に内容を書き換えられるリスクがある。。。
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になる。。。
こうした課題を解決するため、令和2年7月10日から、全国の法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる制度がスタートしました。手数料は1件につき3,900円で、安心して遺言書を預けることができます。
遺言書情報証明書ってどういうときに使うの?
さて、ここからが本題です。
今回ご説明するのは、この制度を利用していた方が亡くなった後、相続人が「どんな内容の遺言書が法務局に保管されているのか」を確認するための手続きです。この確認方法のひとつが、遺言書情報証明書を取得することです。ちなみに、もうひとつの方法は、法務局で直接遺言書を閲覧することです。
遺言書が保管されていることを知るには?
「そもそも、故人が遺言書を法務局に預けていたことって、どうやってわかるの?」と疑問に思うかもしれません。これには主に3つのケースがあります。
法務局からの通知
遺言者本人が「この人に知らせてほしい」と指定していた場合、法務局からその指定された方へ「遺言書が保管されていますよ」というお知らせが届きます。
相続人等がアクションを起こした際の法務局からの通知
上記のように相続人が法務局にて閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けると、他の相続人に対して、法務局から他の相続人全員にその旨の通知が届きます。
自分で確認
「もしかして遺言書があるかも?」と気になった場合、「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることで、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。
遺言書情報証明書の取得手続きの流れ
遺言書が保管されていることがわかったら、いよいよ「遺言書情報証明書」の交付請求手続きを進めます。
誰が手続きできるの?
この手続きができるのは、①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方、②これらの方の親権者や後見人等の法定代理人のみです。司法書士などの専門家が代理で手続きをすることはできません。但し、司法書士は交付請求書の作成をすることはできますので、ご相談頂けましたら幸甚でございます。
請求の方法
請求方法は法務局の窓口に行くか、郵送の2つです。
法務省のウェブサイトによると、郵送は予約不要で待ち時間もないのでおすすめとされています。今回は、この郵送での手続きを前提にご説明します。
請求に必要なもの
交付請求書
法務局のウェブサイトからダウンロードできます。必要事項をパソコンで入力して印刷しましょう。
請求する方の情報: 住所、氏名、生年月日、電話番号
故人(遺言者)の情報: 住所、本籍、氏名、生年月日、死亡年月日
保管情報: 遺言書が保管されている法務局と保管番号(保管されている旨の通知書に記載されています)
手数料: 1通1,400円分の収入印紙を貼ります。
交付請求書作成者:司法書士等を記載します。
相続人全員の氏名、住所、生年月日: 「法定相続情報一覧図」という書類を一緒に提出する場合は、この入力は省略できます。
添付書類
戸籍謄本や住民票の写しなど、請求者と故人との関係を証明する書類をいくつか準備する必要があります。ただ、法定相続情報一覧図があれば、この書類ひとつでOKなのでとてもスムーズです。
返信用封筒
郵送で請求するため、返信用の封筒も忘れずに同封しましょう。宛名は、請求者本人の住所と氏名を記入します。
以上が、遺言書情報証明書の交付請求手続きの流れとなります。
手続きをスムーズに進めるポイント
この手続きで一番手間がかかるのは、相続人全員を正確に特定することです。
ただ、法定相続情報一覧図を同時に作成しておけば、遺言書情報証明書の交付請求に必要な書類がとてもシンプルになります。相続人調査や書類の準備に不安がある場合は、専門家である司法書士に相談するのもひとつの方法です。
私たち司法書士は、普段から相続登記手続きの中で相続人調査のサポートをしていますので、遺言書情報証明書の交付手続きについても、きっとお役に立てるはずです。何かお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。